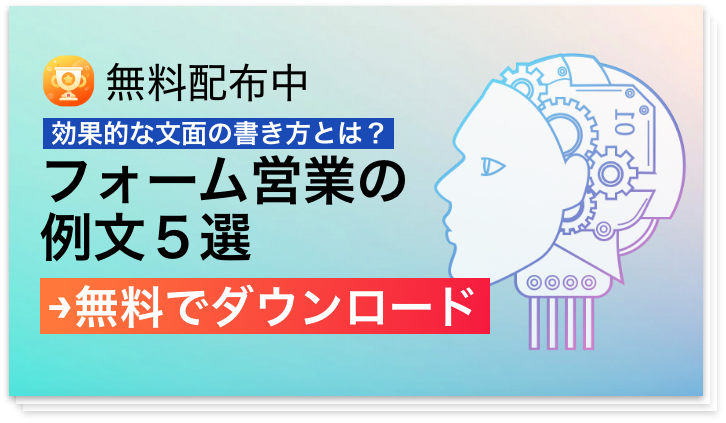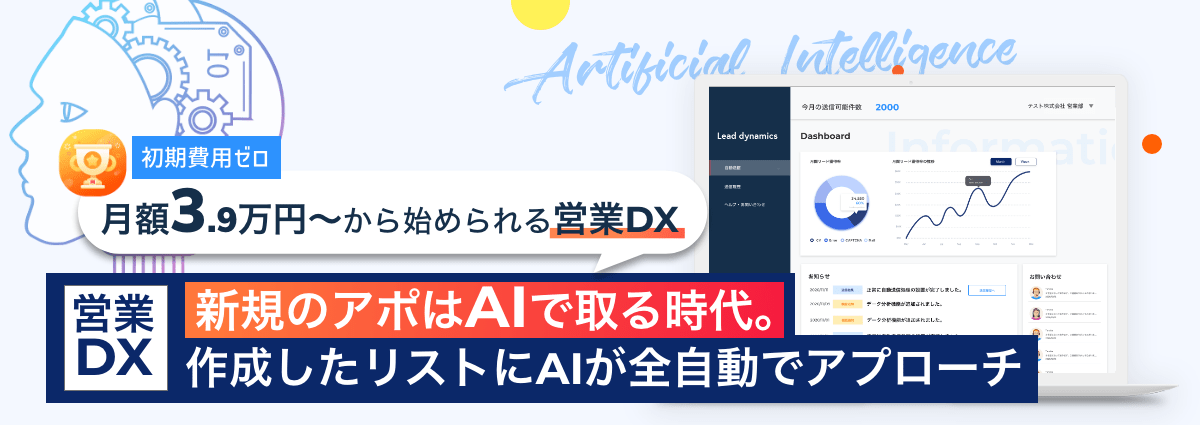
"Human Enhancement with creativity."
体験を豊かに世の中を滑らかに
スポンサー 獲得 営業の全体像
本記事で解決できる課題
スポーツチームや文化団体、イベント運営組織にとって、スポンサー獲得は収益基盤を支える重要な活動です。しかし、多くの組織が「どの企業にアプローチすべきかわからない」「提案しても断られる」「継続契約につながらない」といった課題を抱えています。
本記事では、スポンサー獲得営業の基礎知識から実践的な戦略、成功事例まで体系的に解説します。具体的には、ターゲット企業の選定方法、効果的な提案資料の作り方、信頼関係を構築するコミュニケーション技術、契約後のフォローアップまで、実務に即した内容を網羅しています。
この記事を読むべき対象者
この記事は以下のような方々を対象としています。
まず、プロスポーツチームや地域スポーツクラブの営業担当者です。限られたリソースで効率的にスポンサーを獲得したい方に、優先順位の付け方や提案の差別化方法を提供します。
次に、文化イベントや音楽フェスティバルの主催者です。スポンサーシップの価値を企業にどう伝えるべきか、具体的なアプローチ手法を学べます。
また、NPOや社会貢献活動を行う団体の責任者も対象です。企業のCSR予算を獲得するための提案ストーリーの作り方を理解できます。さらに、テレアポ代行やインサイドセールスツールを活用した効率的なアプローチ方法にも触れています。
スポンサー 獲得 営業の基礎知識と市場動向
定義と重要性
スポンサー獲得営業とは、企業に対して金銭的または物品的な支援を依頼し、その対価として広告露出やブランディング機会を提供するBtoB営業活動を指します。単なる寄付依頼ではなく、企業のマーケティング目標達成を支援するビジネスパートナーシップの構築が本質です。
重要ポイント:日本のプロスポーツチームの場合、収入全体の30〜50%をスポンサー収入が占めるケースも珍しくありません。企業側にとっても、テレビCMやデジタル広告とは異なる顧客接点を持てる価値があります。
市場規模とトレンド
日本のスポーツスポンサーシップ市場は、2023年時点で約4,000億円規模と推計されています。この10年間で約1.5倍に成長しており、今後も拡大傾向が続くと見られています。
近年の顕著なトレンドとして、従来の看板広告やユニフォームロゴといった「露出型」スポンサーシップから、企業の課題解決に貢献する「価値共創型」へのシフトが進んでいます。例えば、SDGs推進を掲げる企業が、環境配慮型イベントのスポンサーになるケースが増加しています。
また、デジタル技術の進化により、スポンサー効果の可視化が進んでいます。SNSでのリーチ数やエンゲージメント率など、定量的なROI提示が求められるようになり、営業側にもデータ分析力が必要とされています。インサイドセールスツールを活用したデータドリブンな営業戦略も、スポンサー獲得の成功率を高める重要な要素となっています。
対象となる業界・企業
スポンサー獲得営業のターゲットとなる業界は多岐にわたりますが、特に親和性が高いのは以下の分野です。
- 地域金融機関(地方銀行、信用金庫)- 地元密着のスポーツチームとの相性が良く、CSR活動の一環としてスポンサーになるケースが多い
- 不動産・建設業界 - BtoB企業であっても、地域での認知度向上や信頼獲得を目的にスポンサーシップを活用
- 飲料メーカーやスポーツ用品メーカー - 自社製品とスポーツの親和性が高いため、積極的にスポンサー契約を締結
- 自動車ディーラーや通信キャリア - BtoC企業として幅広い層へのリーチを目的に参入
- IT企業やスタートアップ - ブランド認知拡大の手段として、従来にないスポンサー形態を模索
重要なのは、業界の特性だけでなく、個々の企業が抱えるマーケティング課題を理解することです。
🎯 今すぐAI営業革命を始めよう!

月額3.9万円からスタート!
※ クレジットカード不要・即日利用開始可能
スポンサー 獲得 営業における課題と解決策
スポンサー獲得営業において、多くの組織が「ターゲット企業へのアプローチ方法」や「営業効率」に課題を抱えています。従来の飛び込み営業やテレアポだけでは、担当者にリーチすることすら難しく、多大な時間とコストがかかるのが現状です。
こうした課題に対して、近年注目されているのがAIフォーム営業ツール「リードダイナミクス」です。企業のウェブサイトにある問い合わせフォームを通じて、AIが自動的に営業メッセージを送信することで、短時間で数千社へのアプローチが可能になります。従来の営業手法と組み合わせることで、スポンサー獲得営業の効率を劇的に向上させることができます。
リードダイナミクス活用のメリット:営業担当者の負担を減らしながら、より多くの潜在スポンサー企業にリーチできます。特に、地方の中小企業や新興企業など、従来の営業リストに載っていなかった企業への新規開拓に効果を発揮します。データ収集・分析機能により、どの業界・企業規模からの反応が良いかを可視化し、次回以降のターゲティング精度も向上させることができます。
よくある課題
それでは、スポンサー獲得営業で多くの組織が直面する具体的な課題を見ていきましょう。主に4つに集約されます。
第一の課題:「適切なターゲット企業を見つけられない」- 闇雲にアプローチしても成約率は低く、営業リソースを浪費してしまいます。
第二の課題:「スポンサーシップの価値を定量的に説明できない」- 企業の担当者は上司への稟議を通す必要があるため、曖昧な提案では決裁を得られません。
第三の課題:「一度きりの契約で終わり、継続につながらない」- 初回契約は取れても、翌年以降の更新率が低いケースが目立ちます。
第四の課題:「営業担当者のスキルにばらつきがある」- 属人的な営業では、組織全体の成果が安定しません。
これらの課題を放置すると、短期的な収入確保はできても、持続可能な収益基盤は構築できません。
課題が発生する原因
上記の課題が生じる根本的な原因を理解することが、解決の第一歩となります。
ターゲット選定の失敗は、多くの場合「企業のマーケティング戦略を理解せずにアプローチしている」ことが原因です。単に「地元企業だから」「大手企業だから」という理由だけでは、企業側のニーズとマッチしません。効率的なターゲットリサーチには、被リンク営業のノウハウを応用したウェブリサーチ手法も有効です。
価値の定量化ができない原因は、「データ収集・分析の仕組みがない」ためです。観客動員数やSNSフォロワー数などの基礎データすら整備されていない組織も少なくありません。
継続契約につながらない原因は、「契約後のコミュニケーション不足」です。スポンサー企業が期待していた効果を実感できなければ、更新は困難になります。
解決に向けたアプローチ:リードダイナミクスの活用
これらの課題を効率的に解決する手段として、AIフォーム営業ツール「リードダイナミクス」の活用が注目されています。
従来のテレアポや飛び込み営業では、1日に接触できる企業数は限られており、担当者不在や門前払いで時間を浪費するケースが大半でした。しかし、リードダイナミクスを活用すれば、AIが自動的に数千社の問い合わせフォームへアプローチを行い、短時間で膨大な数の潜在スポンサー企業にリーチできます。
スポンサー獲得営業での活用メリット:地方の中小企業や新興企業、これまで営業リストになかった潜在スポンサーへも効率的にアプローチ可能。ターゲット企業のリサーチとフォーム入力・送信を自動化することで、営業担当者は商談準備や関係構築に専念できます。
さらに、リードダイナミクスは営業活動のデータ可視化にも貢献します。どの業界・企業規模で反応率が高いか、どんなメッセージが効果的かといったデータが蓄積されるため、PDCAサイクルを回しながら営業戦略を最適化できます。
継続契約率の向上にも効果的です。初回アプローチで獲得した企業データを活用し、四半期ごとのフォローアップメッセージを自動送信することで、関係性を維持しながら契約更新や追加提案の機会を創出します。
営業力の底上げには、リードダイナミクスで得られた成功パターンを社内で共有し、提案資料やメッセージのテンプレート化を進めます。被リンク営業やテレアポ代行などの他の営業手法と組み合わせることで、より包括的なアプローチが可能になります。
効果的なスポンサー 獲得 営業の戦略
戦略設計の基本
効果的なスポンサー獲得戦略は、自組織の強みと企業のニーズを的確にマッチングさせることから始まります。
まず、自組織の「スポンサーシップアセット」を棚卸しします。アセットとは、企業に提供できる価値のことで、看板広告枠、SNS投稿、イベント協賛権、選手とのコラボ企画など多岐にわたります。これらを一覧表にまとめ、それぞれの推定リーチ数や費用対効果を算出します。
次に、スポンサーシップを複数のパッケージに分類します。例えば「プラチナパートナー(年間500万円)」「ゴールドパートナー(年間200万円)」「シルバーパートナー(年間50万円)」といった階層構造を作ることで、企業側も予算に応じて選択しやすくなります。
戦略のポイント:単年度の売上最大化だけでなく、中長期的な関係構築を重視することも戦略の要です。初回は小規模契約でも、成果を実証し信頼を得ることで、翌年以降の増額や複数年契約につなげます。
ターゲット選定のコツ
やみくもにアプローチするのではなく、成約可能性の高い企業を見極めることが重要です。
最も基本的な判断軸は「地理的親和性」です。地域密着型のスポーツチームであれば、まず地元企業を優先します。本社が遠方でも、支店や営業所が活動エリアにある企業も候補となります。
次に「業界・商材との親和性」を確認します。スポーツチームならスポーツ用品メーカーや飲料メーカー、音楽イベントなら楽器メーカーや配信サービスといった具合です。
「企業の成長フェーズ」も重要な判断材料です。急成長中のスタートアップや、新市場参入を図る企業は、認知拡大のためにスポンサーシップを積極活用する傾向があります。
また「過去のスポンサー実績」を調べることで、スポンサーシップに対する企業の姿勢がわかります。同業他社や類似イベントのスポンサー経験がある企業は、提案を理解しやすく、成約率も高まります。
アプローチ手法の選択
ターゲット企業が決まったら、最適なアプローチ手法を選択します。
最も効果的なのは「紹介経由」のアプローチです。既存スポンサー企業や理事会メンバー、地域の商工会議所などを通じた紹介は、信頼度が高く、初回面談の設定率が飛躍的に上がります。
紹介ルートがない場合は「イベント招待」が有効です。試合観戦や発表会への招待を通じて、実際の雰囲気や観客の熱量を体感してもらうことで、提案の説得力が増します。
デジタル時代においては「SNSでの接触」も無視できません。企業の公式アカウントと相互フォローし、投稿に反応することで関係性を築いてから、DMで面談を打診する手法も一定の成果を上げています。
従来型の「コールド営業(飛び込み・テレアポ)」は、スポンサーシップ営業においては成功率が低い傾向にあります。ただし、明確なターゲットリストと練られたトークスクリプトがあれば、初回接触の手段として機能する場合もあります。効率的にアプローチ数を増やしたい場合は、テレアポ代行会社の活用も選択肢の一つです。
スポンサー 獲得 営業の具体的な手順とプロセス
準備フェーズでやるべきこと
成功する営業活動は、入念な準備から始まります。
まず「企業研究」を徹底します。ターゲット企業のウェブサイト、IR資料、プレスリリースを読み込み、事業内容、経営方針、最近の取り組みを把握します。特に注目すべきは、企業が掲げる中期経営計画やマーケティング戦略です。
次に「キーパーソンの特定」を行います。大企業の場合、広報部、マーケティング部、CSR推進部など、複数の部署が関与する可能性があります。LinkedInやFacebook、業界紙の記事から、意思決定権を持つ人物を見極めます。
「提案ストーリーの設計」も準備段階で固めておきます。単なるメニュー表の提示ではなく、「貴社の〇〇という課題を、当団体の△△という強みで解決できる」という論理構成を作ります。
また「想定Q&Aの作成」も欠かせません。「費用対効果は?」「過去の事例は?」「競合他社も参加しているか?」といった質問に即答できるよう、データと事例を準備します。
実行フェーズの進め方
準備が整ったら、実際のアプローチを開始します。
初回コンタクトでは「短く、価値を明確に」を心がけます。メールであれば3〜4行、電話であれば1分以内で、「誰が」「何のために」「何を提案したいのか」を伝えます。この段階では詳細説明は不要で、面談の約束を取ることだけに集中します。
初回面談では「8割ヒアリング、2割提案」を原則とします。企業が現在注力していること、課題に感じていること、過去のスポンサー経験などを丁寧に聞き出します。この情報が、次回の提案をカスタマイズする材料となります。
面談後24時間以内に「お礼メールと次回提案の予告」を送ります。「本日お伺いした〇〇の課題に対し、当団体としてこのような提案が可能です」と簡潔に述べ、次回面談の日程調整を打診します。
2回目の面談では「具体的な提案資料」を持参します。ヒアリング内容を反映したカスタマイズ提案であることを強調し、単なるパッケージ販売ではないことを示します。
フォローアップの重要性
契約締結後のフォローアップこそが、継続契約と口コミ紹介を生む鍵です。
契約直後に「キックオフミーティング」を設定し、今後のスケジュール、担当者、連絡体系を確認します。この段階で「成果測定の指標」を企業と合意しておくことが重要です。
契約期間中は「月次レポート」を提出します。看板の露出回数、SNSでの言及数、イベント参加者数など、合意した指標の実績を報告します。数値が目標に届いていない場合でも、隠さず報告し、改善策を提案する姿勢が信頼につながります。
また「追加価値の提供」を積極的に行います。契約範囲外であっても、企業にメリットがあると判断したら、SNSでの特別投稿や選手のサプライズ訪問などを提案します。こうした「期待を超える対応」が、継続契約の決め手となります。
🎯 営業効率を劇的に改善!

月額3.9万円からスタート!
※ クレジットカード不要・即日利用開始可能
成功事例とベストプラクティス
事例1: 大手企業の場合
大手飲料メーカーA社とサッカーJリーグBクラブの提携事例を紹介します。
Bクラブは、地方都市を拠点とする中堅クラブで、観客動員数は平均8,000人程度でした。全国ブランドであるA社にアプローチする際、単なる「看板広告の提供」では差別化できないと判断しました。
そこで、A社が注力していた「健康志向商品の認知拡大」という経営課題に着目しました。Bクラブは、試合前に親子で参加できるランニングイベントを企画し、A社の健康飲料を公式ドリンクとして提供する提案を行いました。
さらに、地域の小学校と連携し、食育プログラムにA社の栄養士を派遣する企画も盛り込みました。これにより、A社は単なる広告露出だけでなく、「地域の健康づくりに貢献する企業」というブランドイメージを構築できると判断し、年間1,000万円の契約が成立しました。
成功のポイント:初年度は親子ランニングイベントに500組が参加し、地元メディアでも大きく取り上げられました。A社の担当者は「ブランド好感度調査で地域内の数値が10ポイント上昇した」とコメントしています。契約は3年目も継続し、金額も1,500万円に増額されました。
事例2: 中小企業の場合
地方の工務店C社と、地域密着型のバスケットボールチームDチームの提携事例です。
C社は従業員30名の中小企業で、スポンサーシップの経験はありませんでした。Dチームの営業担当者は、C社が「若手人材の採用難」に悩んでいることをヒアリングで把握しました。
そこで、「スポーツを通じた採用ブランディング」という切り口で提案を行いました。具体的には、C社の社名入りユニフォームでの試合出場、試合会場でのブース出展、さらにC社の新卒採用イベントに選手が参加し、学生と交流するという内容です。
年間契約金額は50万円と小規模でしたが、C社にとっては「地元の人気チームとつながっている会社」というイメージが構築され、説明会への学生参加者が前年比30%増加しました。
2年目は契約を継続し、C社の施工物件の現場見学会と試合観戦をセットにしたイベントも実施しました。これにより、C社は単なる広告宣伝費としてではなく、「人材採用・育成費」の一部としてスポンサー費用を計上できるようになりました。
成功要因の分析
上記2つの事例に共通する成功要因を分析すると、以下の4点が浮かび上がります。
第一に、「企業の経営課題を起点に提案を設計している」点です。スポンサーシップを「広告枠の販売」と捉えるのではなく、「企業の課題解決手段」として位置づけることで、決裁者の納得を得やすくなります。
第二に、「定量的な成果指標を設定している」点です。A社の事例ではブランド好感度、C社の事例では採用応募者数という、企業側が重視する指標で効果を測定しています。
第三に、「契約後も継続的にコミュニケーションを取っている」点です。両事例とも、年に数回の対面ミーティングを実施し、企画の改善や追加施策の提案を行っています。
第四に、「小さく始めて大きく育てる」アプローチを取っている点です。特にC社の事例では、初回は50万円という手の届く金額から始め、成果を実証してから関係性を深めています。
導入事例
株式会社アットオフィス:ROI1800%の衝撃成果
「もっと効率よく営業を仕掛けたい」という課題を抱えていたアットオフィスでは、営業リストの整備さえできれば、3分で1000件以上にアプローチできるというスピード感に惹かれて「リードダイナミクス」を導入しました。
実際に導入後は、月5〜10件のアポイントを獲得し、受注額は450万円規模に到達。商談1件あたりの獲得コストはわずか25,000〜50,000円程度に抑えられ、ROIは1800%という驚異的な数値を記録しました。営業工数の削減とともに、高い成果を両立した典型的な成功例です。
株式会社IXMILE:5倍のアプローチ数を実現
IXMILEでは、それまで1件ずつ営業メールを送る手作業に多くの時間を取られていました。営業リソースに限界を感じていた中、AIを活用して自動化する方法として「リードダイナミクス」の導入を決断。
結果、従来の5倍となる3000件以上のアプローチを一括実行できるようになり、「本当に届けたい相手に、効率よく情報を届けられるようになった」との声も。手動では不可能だった広範囲へのスピーディーなアプローチが実現し、営業活動のスケーラビリティが一気に拡大しました。
Byside株式会社:商談獲得単価11,300円・ROI8,724%
「営業コストの見直し」が急務だったBysideでは、AIによるフォーム営業でどこまで成果が出るかを試す目的で、リードダイナミクスを導入。すると、商談1件あたりの獲得単価は11,300円まで下がり、さらにROIはなんと8,724%という驚異の数値に。
ターゲット企業の抽出からフォーム入力・送信まで、AIがすべてを担ってくれるため、人手を最小限に抑えたまま高成果を出せる営業体制が整いました。「費用対効果の高い営業」が実現できた事例として、多くの企業が参考にしています。
株式会社シグニティ:ライトプランで15件の商談を獲得
スタートアップ期で「どの業種・職種に自社サービスが響くか分からない」という課題を抱えていたシグニティ。まずは月額65,000円で3,500件送信可能な"ライトプラン"から試験導入を行いました。
結果は、1ヶ月で15件の商談を獲得、1件あたり約4,300円という低コストでの商談化に成功。さらに、反応率の高かった業界や職種を分析することで、マーケティング戦略の見直しにもつながり、営業の「次の一手」が見えるようになりました。
これらの成功事例に共通しているのは、「営業活動の属人化を解消」しつつ、「再現性のある仕組み」で成果を出していることです。営業AIツールを導入することで、単にアポ獲得数が増えるだけでなく、
-
営業効率の大幅アップ
-
成果の可視化と最適化
-
コストの削減と投資対効果の最大化
といった複数の価値を同時に実現しています。
今後さらに多くの企業がAIによるアポどりに移行していく中で、「いち早く始めた企業」が先行優位を築けるのは間違いありません。あなたの会社でも、これらの事例をヒントに、営業AI導入の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
スポンサー 獲得 営業で成果を出すためのポイント
信頼関係構築のコツ
スポンサーシップは単発の取引ではなく、中長期的なパートナーシップです。信頼関係の構築が成否を分けます。
最も基本的なのは「約束を守る」ことです。提出期限、連絡のタイミング、成果報告など、小さな約束を確実に守ることで、「この組織は信頼できる」という印象を与えます。
次に「透明性の確保」です。都合の悪い情報も隠さず共有する姿勢が、長期的な信頼を生みます。例えば、観客動員数が目標に届かなかった場合でも、その原因分析と改善策を正直に報告することで、誠実さが伝わります。
また「相手の立場で考える」ことも重要です。企業の担当者は社内で稟議を通す必要があるため、上司への説明に使える資料やデータを積極的に提供します。「あなたの社内評価が上がるように支援する」という姿勢が、強固な関係を作ります。
提案資料の作り方
説得力のある提案資料は、スポンサー獲得の成否を左右します。
資料の構成は「課題→解決策→根拠→実績→条件」の流れが基本です。最初に企業の課題を明示し、「私たちはこう理解している」と示すことで、ヒアリングの成果を伝えます。
次に、その課題を解決する具体的なスポンサーシッププランを提示します。ここでは「貴社専用にカスタマイズした」ことが伝わるよう、企業名や商品名を資料内に盛り込みます。
根拠のセクションでは、数字を多用します。観客の年齢層、居住地域、世帯年収などのデータを示し、「貴社のターゲット層と一致している」ことを証明します。
資料作成のポイント:ビジュアルも重要です。文字だらけのスライドではなく、写真、グラフ、イラストを多用し、視覚的に理解しやすくします。実際の看板設置イメージや、SNS投稿のモックアップを見せると、契約後のイメージが湧きやすくなります。
クロージングの技術
提案が好意的に受け止められても、契約締結まで進めるには適切なクロージング技術が必要です。
まず「決裁プロセスの確認」を行います。「ご検討いただける場合、社内ではどのようなステップで意思決定が進みますか?」と質問し、誰の承認が必要で、どれくらいの時間がかかるかを把握します。
次に「次のアクション」を明確にします。「では、来週中に社内でご検討いただき、その結果を再来週の月曜にお伺いする形でよろしいでしょうか?」と、具体的な日時を提案します。
もし即答を避ける様子があれば、「懸念点」を引き出します。「もし何か不明な点やご懸念があれば、今お聞かせいただければ、次回までに資料を補足します」と伝え、ためらいの原因を明確にします。
失敗を避けるための注意点
よくある失敗パターン
スポンサー獲得営業で繰り返し見られる失敗パターンを知ることで、同じ轍を踏まずに済みます。
最も多いのが「一方的な売り込み」です。企業のニーズを聞かずに、用意した提案をそのまま押し付けると、「押し売り」と受け取られ、門前払いになります。
次に「価値の過大評価」があります。「当チームは地域で絶大な人気がある」「SNSで必ずバズる」など、根拠のない誇張は、後で信頼を失う原因となります。
また「競合の軽視」も失敗を招きます。同じ企業に複数の団体がアプローチしている場合、自組織だけの情報で提案すると、比較検討で負けてしまいます。
避けるべき行動
具体的に避けるべき行動を列挙します。
- 事前調査なしのアプローチ - 企業のウェブサイトすら見ずに訪問すると、「うちのことを何も理解していない」と思われます
- 価格交渉での安易な値引き - 最初に高額を提示し、渋られたら大幅値引きする手法は、不信感を生みます
- 競合他社の批判 - ネガティブ営業は、自組織の品位を下げます
- 曖昧な表現の多用 - 「多くの方に見ていただけます」といった曖昧な表現は説得力に欠けます
- 返信の遅延 - 企業からの問い合わせに24時間以上返信しないと、信頼を損ないます
リスク管理の方法
スポンサーシップ営業にはリスクも伴うため、適切な管理が必要です。
まず「契約内容の明文化」を徹底します。口頭での約束は後で「言った言わない」の問題になるため、すべて契約書または覚書に記載します。
次に「過度な依存の回避」です。1社のスポンサー収入が全体の50%を超えると、その企業の撤退時に経営が危機に陥ります。複数企業に分散させることでリスクヘッジします。
「反社チェック」も不可欠です。契約前に企業の評判を調べ、反社会的勢力との関わりがないか確認します。
よくある質問(FAQ)
スポンサー獲得営業に必要な経験やスキルは?
スポンサー獲得営業は、一般的なBtoB営業経験があれば取り組めます。特に、無形商材(広告、コンサルティングなど)の営業経験がある方は、スポンサーシップという「目に見えない価値」を売る感覚が掴みやすいでしょう。
必須スキルとしては、第一に「ヒアリング力」、第二に「提案書作成力」、第三に「データ分析力」が求められます。また、スポーツや文化への情熱も大切ですが、ビジネスとしての成果を出す意識とのバランスが重要です。
小規模な組織でも大手企業のスポンサーを獲得できる?
結論から言えば、可能です。ただし、大手企業が求める価値を正しく理解し、それに応える提案をすることが前提となります。
小規模組織の強みは「地域密着性」と「小回りの良さ」です。全国規模のチームでは対応できないような、地域特化型の企画や、スピーディーなカスタマイズ対応が可能です。
大手企業の地方支店や営業所は、本社とは異なる独自のマーケティング課題を抱えていることがあります。小規模でも、地域の学校や福祉施設と連携した社会貢献プログラムを提案できれば、大手企業の関心を引けます。
スポンサー契約の適正価格はどう決める?
スポンサー契約の価格設定は、多くの組織が悩むポイントです。絶対的な正解はありませんが、以下の要素を総合的に考慮します。
まず「市場相場」を調べます。同規模のチームやイベントが、どの程度の金額で契約しているかを、公開情報や業界ネットワークから収集します。
次に「提供価値の積算」を行います。看板広告であれば、設置場所の視認回数×広告単価で計算します。SNS投稿であれば、フォロワー数×エンゲージメント率から推定リーチを算出し、デジタル広告の相場と比較します。
また「企業の予算感」も考慮します。大手企業と中小企業では、マーケティング予算の規模が桁違いです。同じ内容でも、相手に応じて価格帯を調整する柔軟性が求められます。
契約更新率を高めるにはどうすればいい?
契約更新率の向上は、スポンサー獲得営業において最重要課題の一つです。新規獲得よりも既存維持の方がコストが低く、安定収益につながるためです。
最も効果的なのは「期待を超える成果の提供」です。契約時に約束した以上の価値を提供することで、企業側の満足度が高まります。
次に「定期的なコミュニケーション」です。契約期間中に最低でも四半期に1回は対面またはオンラインでミーティングを設定し、進捗報告と意見交換を行います。
「データに基づく効果報告」も不可欠です。曖昧な「たくさんの方に見ていただけました」ではなく、「看板の前を通過した推定人数は年間10万人、SNS投稿のリーチは累計5万人」といった具体的な数値で示します。
断られた企業に再アプローチするタイミングは?
一度断られた企業への再アプローチは、適切なタイミングと方法を選べば成功する可能性があります。
まず「断られた理由」を明確にすることが出発点です。「予算がない」「タイミングが合わない」「提案内容が響かなかった」など、理由によって再アプローチの戦略が変わります。
予算的な理由で断られた場合は、「次年度の予算編成期」が再アプローチのタイミングです。多くの企業は年度初め(4月)や下半期開始時(10月)に予算が新たに配分されるため、その2〜3ヶ月前に接触すると効果的です。
タイミングが合わなかった場合は、「6ヶ月〜1年後」が目安です。その間、定期的に情報提供(ニュースレター、イベント案内など)を続け、関係を途切れさせないことが重要です。
まとめ
スポンサー獲得営業は、単なる資金調達活動ではなく、企業のマーケティング課題を解決するビジネスパートナーシップの構築です。成功の鍵は、自組織の売りたいものを押し付けるのではなく、企業が本当に必要としている価値を提供することにあります。
本記事で解説した内容を実践に移すために、以下の3つのアクションを今日から始めてください。
アクション1: 自組織の「スポンサーシップアセット」を棚卸しする
今週中に、提供できる価値(看板、SNS、イベント協賛権など)をすべてリストアップし、それぞれの推定リーチ数や想定価格を算出してください。これが営業活動の基盤となります。
アクション2: ターゲット企業リストを作成し、優先順位をつける
地理的親和性、業界親和性、過去のスポンサー実績などの基準でスコアリングし、上位20社をリストアップしてください。やみくもなアプローチではなく、成約可能性の高い企業に集中することで、効率が劇的に向上します。
アクション3: 既存スポンサー企業に満足度ヒアリングを実施する
今月中に、現在契約中のスポンサー企業すべてに連絡を取り、「現在の取り組みについてどう感じているか」「改善してほしい点はないか」をヒアリングしてください。新規獲得よりも既存維持が収益安定の鍵です。
スポンサー獲得営業は、一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、企業との信頼関係を一つひとつ丁寧に築き、約束した価値を確実に提供し続けることで、持続可能な収益基盤が構築できます。
また、効率的な営業活動を実現するためには、インサイドセールスツールやテレアポ代行、被リンク営業などのデジタル施策を組み合わせることも有効です。本記事の内容を参考に、貴組織ならではのスポンサーシップ戦略を確立してください。
フォーム営業AIツールの「リードダイナミクス」の特徴
問い合わせフォーム営業AIツール「リードダイナミクス」とは
リードダイナミクスはエンド開拓のための革新的なAIツールです。このツールは以下の特徴を備えています。エンド開拓を効率化するには同時刻に数千件、予約送信ができるAI搭載のSaasをお使いください。
前述の通りですが、できるだけ午前中にまとまった件数を送信することでアポ獲得率を高めます。 一気に1000社送るのは到底、人の力では難しいですし、もし送信担当の方が病気などで会社を欠席した場合は送信できません。 予約送信を活用しAIに任せる事で、送信担当が寝坊しても欠席しても定刻になれば送信処理が自動で開始されます。
それを実現できるのがフォームマーケティング自動化ツールの「リードダイナミクス」です
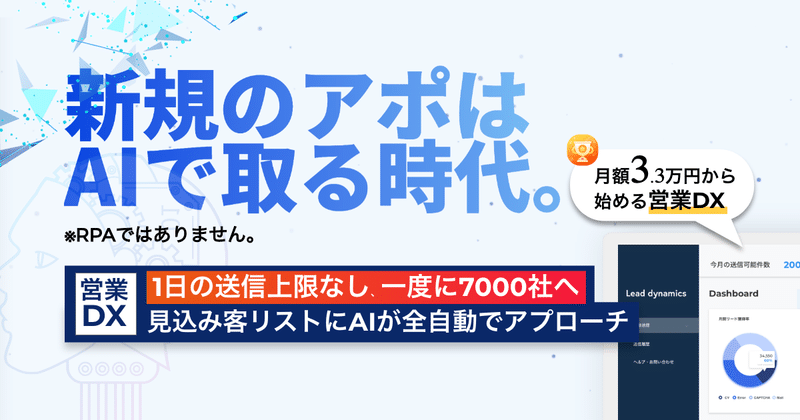
リードダイナミクスの特徴 【国内トップクラスの送信スピード、送信成功率を誇ります。】
https://lead-dynamics.com/■RPAではなく機械学習を施したAIがターゲット企業のお問い合わせフォームを検知し、 記入から送信まで全自動で実行可能。
■作業時間約3分で1000件アプローチ(予約機能を使えば一度に7,000件アプローチが可能です)
■1日の送信上限なし。プラン内の件数であれば何件でも送信可能です。
■SPA(シングルページアプリケーション)で構築されている為、滑らかに動く快適なUIになっており、 送信処理も全てクラウドで行う為、PCに負荷がかかりません。
■送信成功率 約50〜80%(弊社調査による)。
■機械学習を施したAIが送信するため日々送信成功率は向上していきます。
■フォーム付近の営業NG文言を自動検知し除外。1週間以内に送信している企業に送る際は注意喚起(アラート表示)
■送信失敗は送信可能件数から差し引かれません (選択されたプランの料金はいただきますが、 システム上は送信失敗は送信可能件数から差し引かれません)。
■送信できなかった場合の理由を送信結果の詳細に明記。
※詳しくは、サービスサイトをご覧ください。
人力で1000件送ろうと思うと大変ですよね? その必要はありません。AIが全て作業を代行してくれます。
送信成功率 約50%〜80%

様々なお問い合わせフォームを学習
RPAではなく弊社Saasには機械学習を施したAIが搭載されております。
その為高い送信成功率が特徴です。
日々AIが様々な形式のフォームを学習しておりますので今後更に送信成功率は上昇します。
国内複数のお問い合わせフォームを学習させたデータや、NGワード等の検出をデフォルトで提供することで、モラルを保ちつつ学習データを駆使し様々なレパートリーのお問い合わせフォームに送信する事が可能です。
※本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証致しません。※送信成功率は、自社調べでありシステムエラーによりブラウザの起動失敗、お問い合わせページが特定・アクセスできない、プライバシーが保護されない、キャプチャで保護されたページ、入力失敗、送信・確認ボタンの特定・クリックができない、送信先に起因、関連する予期せぬエラーを除いて算出。
営業禁止は自動除外
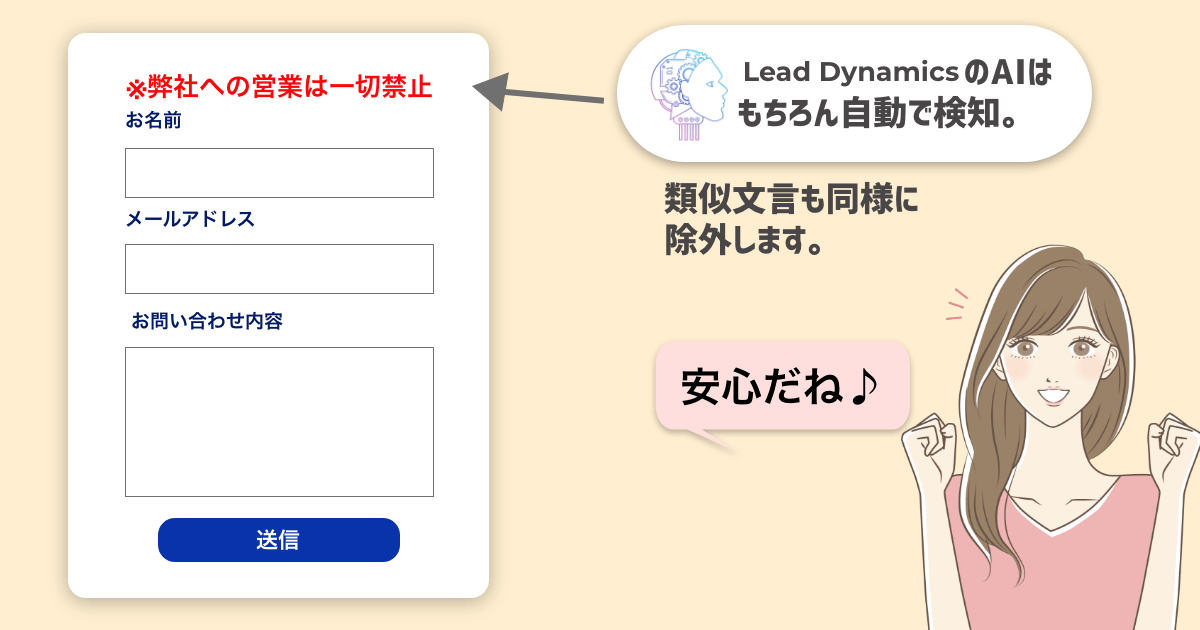
フォーム付近に営業禁止文言がある場合、送信除外
フォーム付近に「営業はご遠慮ください」などの文言が明記されている場合、類似文言含めAIが自動で検知し送信除外しております。
何度も同じ会社に送らないように、注意喚起
同じ企業に何回も送られないように送信しようとしたリストに直近1週間以内に送信された企業が含めれている場合は注意喚起のアラートが表示されます。
システマチックにNGリストを管理できる為、ヒューマンエラーを未然に防ぐ事ができます。
NGリストに登録されている企業様は送信除外
SaaSにNGリストを登録できる為、NGリストに登録しておけば今後一切その企業には送らない設定が可能です。 すでにお取引がある企業様などをNGリストに登録しておくと事前にリスト被りを防げます。また、何名かでリードダイナミクスを利用する際もNGリストが一元管理されているのでチームで送る際はとても便利です。
問い合わせフォーム自動送信AIツール導入企業様の声
実際に問い合わせフォーム自動送信AIツールの「リードダイナミクス」を導入していただいた企業様にインタビューを行ってみました。
問い合わせフォーム自動送信AIツールのまとめと今後の展望
2023年は、AI技術の進化とビジネス環境の変化により、リード獲得の方法にも大きな動きが見られました。この記事を通して、私たちは多くのリード獲得AIツールの紹介やその利点、さらには選定のポイントや実際の導入事例などを深く掘り下げてきました。 法人営業担当者への最終的なアドバイス 最後に、法人営業担当者の皆さんへのアドバイスとして、以下の3つのポイントを心に留めておくことをおすすめします。- ニーズの特定: どのようなリードを獲得したいのか、具体的なニーズを明確にすることが最も重要です。その上で、適切なAIツールを選定することができます。
- 継続的な学習: AIツールの導入は、一度きりのものではありません。市場や技術の変化に合わせて、ツールの更新や改善を継続的に行うことが必要です。
- 効果測定: AIツールの導入後、定期的にその効果を測定し、必要に応じて改善策を検討することで、より高いリード獲得効果を実現できます。
ContactUs
導入をご希望の方はこちらからお問い合わせください
貴社サービスの成長をLeadDynamicsが支援致します。